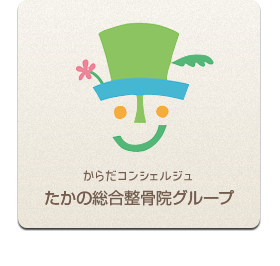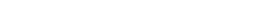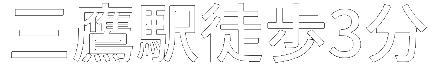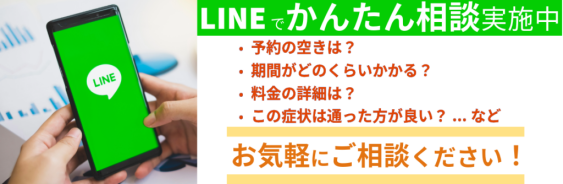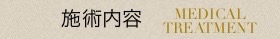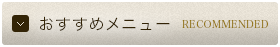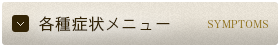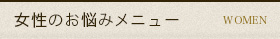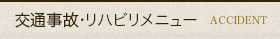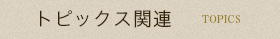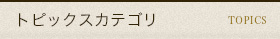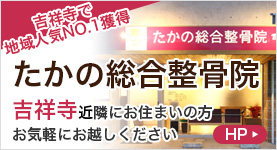肩こりや首の緊張でお悩みの方に治療を行い、筋肉の緊張をほぐしている治療院が多いです。施術が終わった直後は「肩が軽くなった」「首が回るようになった」と多くの方が笑顔になります。しかし、せっかく力が抜けても、数日後にはまた肩が上がって緊張していることがあります。
なぜ同じことが繰り返されてしまうのか。
理由はひとつではありませんが、その背景には姿勢や使い方、そして「呼吸と肩の力みの脳内リンク」が隠れていることがあります。
呼吸と肩の緊張は脳で神経が結びついてしまう
肩に力が入っている人の多くは、無意識のうちに呼吸のたびに肩を持ち上げています。吸うときに肩がすくむ、吐くときに肩が下がる。この呼吸のクセは小さな動きに見えますが、何十年も繰り返すと肩の筋肉が常にスタンバイ状態になります。
そして脳の中では、「呼吸=肩を持ち上げる動作」と結びついてしまいます。
結びつくと言っても物理的にくっつくわけではありません。
あなたは歩いている時にひとつひとつの筋肉を順番に動かしている感覚はありますか?
これは歩行という動作を繰り返している事で少しずつ使う筋肉を脳にインプットして自然と考えずに歩けるようになります。
人間は生まれてから1年数ヶ月をかけて歩けるよう神経回路を作り上げていくので、忘れることはほぼないと思います。
そして、あなたはデスクワークで肩に力が入ったまま呼吸していた期間はどれくらいですか?
おそらくこのブログを見た方は年単位でインプットし続けているのではないかと思います。
そうなると、施術で肩の筋肉をほぐし、一時的に力が抜けても、いざ普段の呼吸に戻ったとき、脳が自動的に肩に指令を出してしまうのです。
これを改善していくには正しい使い方をして、その方が身体にとって楽だという認識を植え付けていくしかありません。

なぜ肩に力が入る?
肩に力が入る理由は姿勢です。
姿勢が猫背になると頭が前にいきます。それを支えるためには首肩が緊張する必要があります。
猫背姿勢は体幹としては前で支えます。実際にやってみていただくとお腹と胸に力が入るのがわかるかと思います。
その結果、胸に肩が引っ張られ肩は負けないように力が入ります。
猫背姿勢が続くと、肩の緊張が続くため血流が悪くなり痛みやコリ感になります。
肩は姿勢によって負担がかかっている犠牲者です。
その姿勢の結果、支えるために頑張っている肩を緩めたらどうなるでしょう?
治療だけでは足りない「脳の再教育」
肩こりや首こりの慢性化は、単なる筋肉の硬さではなく、「脳と身体の使い方の癖」が深く関わっています。肩に力が入るクセが長年続いた結果、脳の神経回路に定着しているのです。
治療で筋肉を緩めても、脳の回路が書き換わらないままでは使い方は変わらず、すぐに元通りに戻ります。
だからこそ「呼吸で肩に力を入れない」という新しい使い方を脳に学習させることが大切です。
この再教育は時間がかかります。しかし、あきらめずに呼吸を練習し続けることで、少しずつ肩に力が入らなくなり、治療の効果も長持ちします。
心と呼吸の深いつながり
もうひとつ大切なのは、心の状態も呼吸と肩に影響を与えることです。
緊張しているときや不安を感じるとき、人は無意識に呼吸が浅くなります。浅い呼吸では酸素を取り入れにくくなるため、脳が「危険を察知した」と判断し、交感神経が優位になります。肩は肋骨を頑張って持ち上げる作用があります。すると、肩がさらにすくみ、首が硬くなる悪循環が起きます。
逆に、深くてゆったりした呼吸は「今は安心して大丈夫」というメッセージを脳に送ります。肩も自然と下がり、身体全体がリラックスしやすくなります。
呼吸を整え、治療効果を長持ちさせよう
「何度治療を受けても肩がすぐに硬くなる」と感じている方は、まずご自身の呼吸を観察してみてください。
・息を吸うとき、肩が上がっていませんか?
・胸ばかりが動いていませんか?
・呼吸が浅く、速くなっていませんか?
気づくことが改善の第一歩です。
呼吸と肩の力みを切り離す意識を持ち、日々の生活で腹式呼吸を心がける。それだけでも肩の緊張は変わっていきます。
治療はあくまできっかけであり、最後の仕上げは日々の呼吸と意識です。当院では施術だけでなく、呼吸の指導やセルフケアのサポートも行っています。
まとめ
深呼吸は単なるリラックス法ではなく、肩の力みを手放す大きな鍵です。
肩こりの改善に、呼吸の質を変えることをぜひ取り入れてみてください。
治療効果を長持ちさせるための呼吸改善の前提として正しい力みのない姿勢が大切です。
三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院では姿勢作りと呼吸を含めた正しい体の使い方をお伝えしております。
根本改善を含めた身体作りをしていきたいと思われた方はぜひお問合せください。